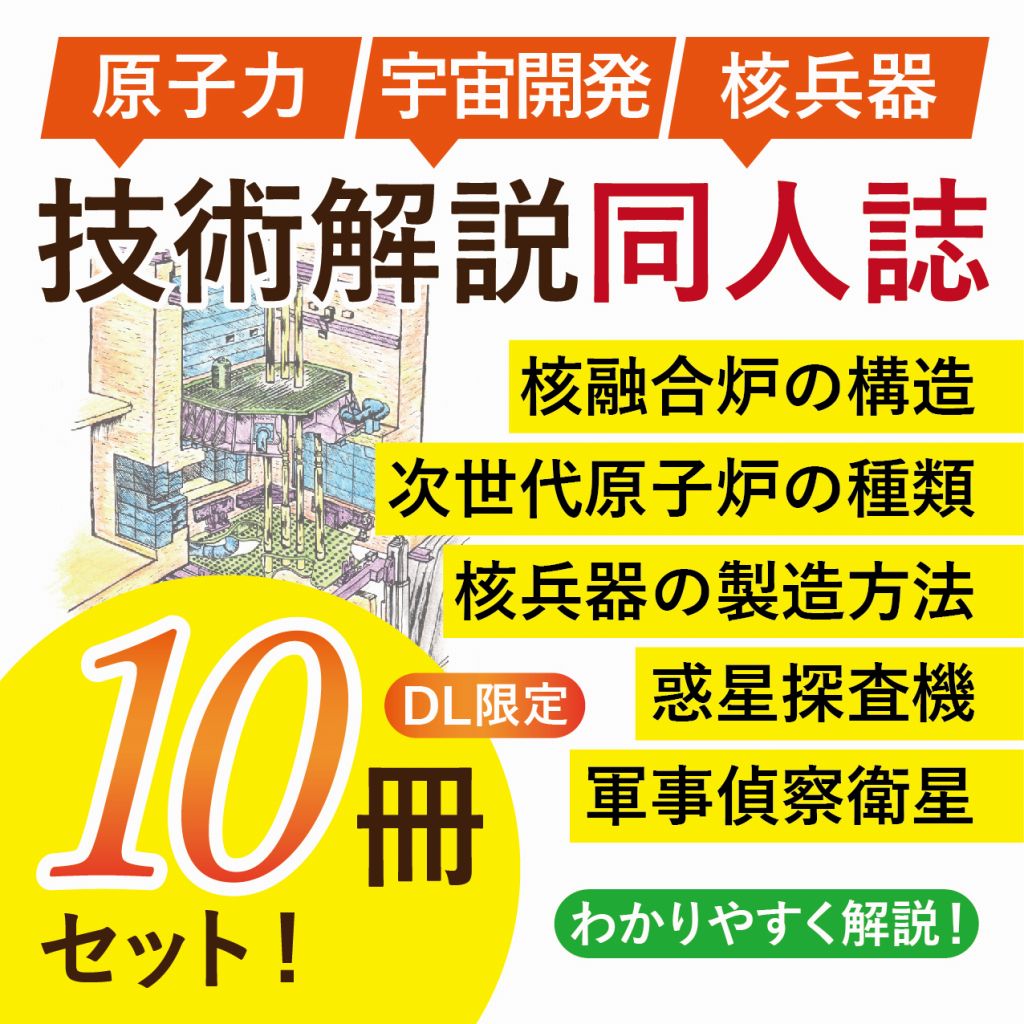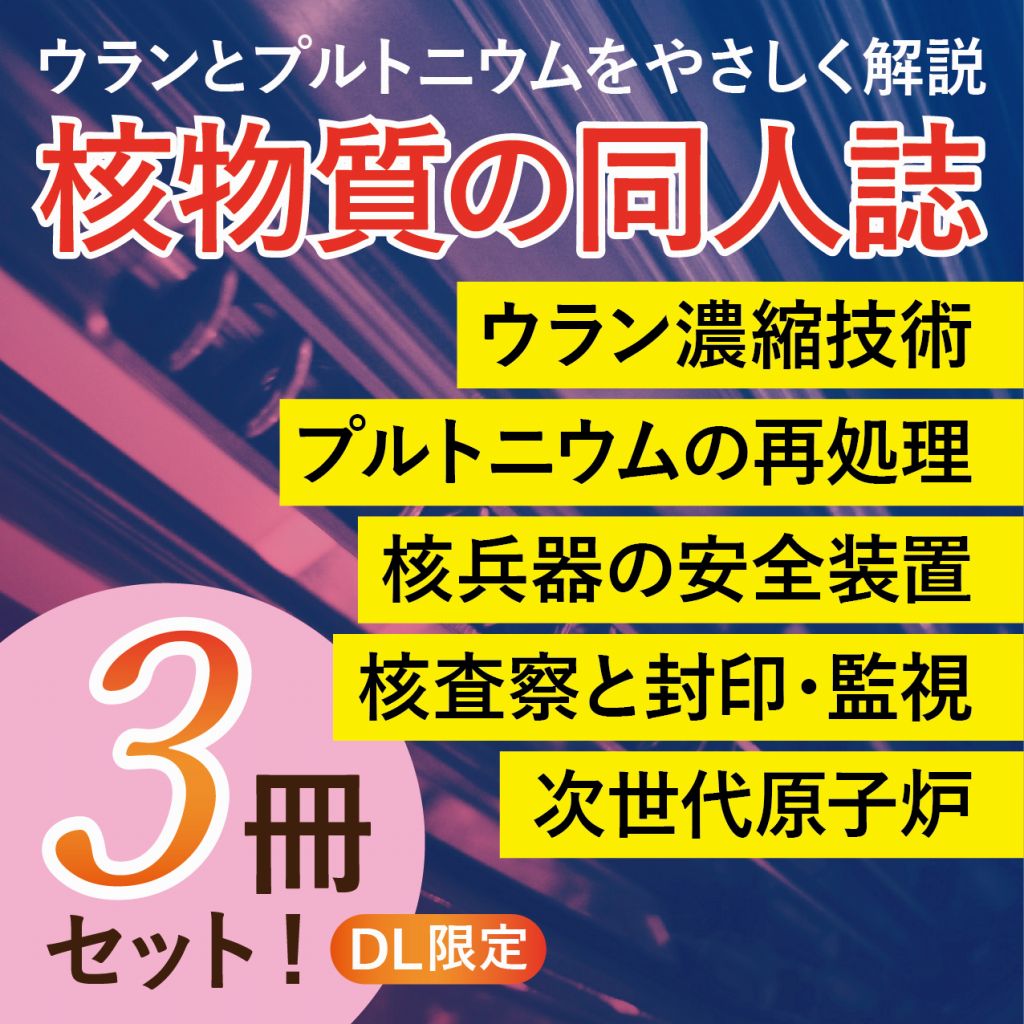ガンマ線観測衛星「コンプトン」
コンプトン衛星はNASAの「グレートオブザーバトリー計画」によって、打ち上げられた人工衛星です。ちなみにこのグレートオブザーバトリー計画では有名なハッブル宇宙望遠鏡も打ち上げられています。1991年にスペースシャトルで打ち上げられており、重量は17トンという非常に大型の人工衛星です。2000年の6月にミッションが終了し、大気圏に再突入しました。
BATSE
衛星の周囲に8基が配置されています。高強度の線源を検知して分光するSD(スペクトロスコピー・ディテクター)と、弱い線源を検知する大面積のLAD(ラージエリア・ディテクター)が備わっています。この装置を使って一日に約一回ガンマ線バーストが検出されていました。そしてガンマ線バーストの発生場所は全天で一様に生じていることがわかりました。
OSSE
4つの検出器が独立して駆動するタングステン・コリメーター付きのシンチレーター検出器です。バックグラウンドの影響を減らせるように、シンチレーターはNaIとCsIの2種類を組み合わせた波形弁別を行うフォスウィッチ構造となっています。例えば中性子が入射した場合、発生するシンチレーション光の遅発性分が多くなります。こうした現象を観測することで、中性子とガンマ線を見分けることができるようになるわけです。また、タングステン製のコリメーターが検出器の前に設置されており、観測対象以外からのガンマ線の入射を防いでいます。また、観測対象以外のバックグラウンドも精密に測定し、不要な観測データを除去できるように、2組の検出器で観測対象とバックグラウンドを交互に観測するという運用も行われていました。
COMPTEL
上部に液体シンチレーター、下部にNaIシンチレーターを搭載した検出器です。いわゆるコンプトン望遠鏡と呼ばれるものです。上部の液体シンチレーターでコンプトン散乱を起こしたガンマ線の反跳電子を下部のNaIシンチレーターで検出するというものです。この機器を使って全天マップの作成も行っています。有効面積は小さいが、感度は高い。波形弁別をしたりしている。光子の飛行時間をイベント選択条件にしているため、どうしても観測の視野は狭くする必要があったそうです。アルミニウムの放射性同位体であるアルミニウム26の検出などにも成功しています。
EGRET
スパークチェンバーを使った高エネルギーガンマ線の検出器です。ガンマ線が入射した際の対生成反応を利用しています。スパークチェンバー内部で対生成反応が起きると電子と陽電子が放出されます。スパークチェンバーは金属板が多層に重ねられた構造になっており、その飛跡を観測することでガンマ線の到来方向を知ることができます。下部にはNaIシンチレーターが搭載されており、電子と陽電子によって生じた二次粒子のカスケードシャワーの電離損失を測定することで、ガンマ線のエネルギーを知ることができます。
参考
- http://astro-dic.jp/compton-gamma-ray-observatory/