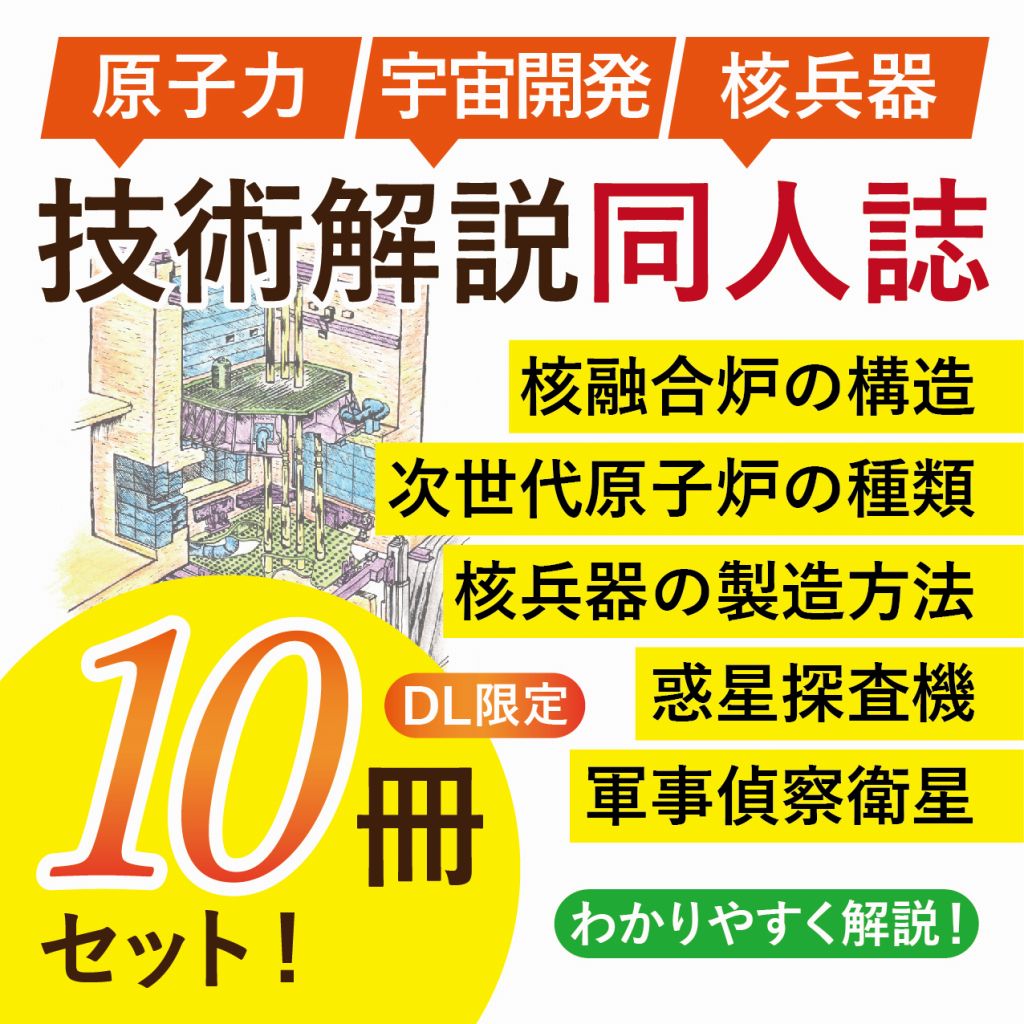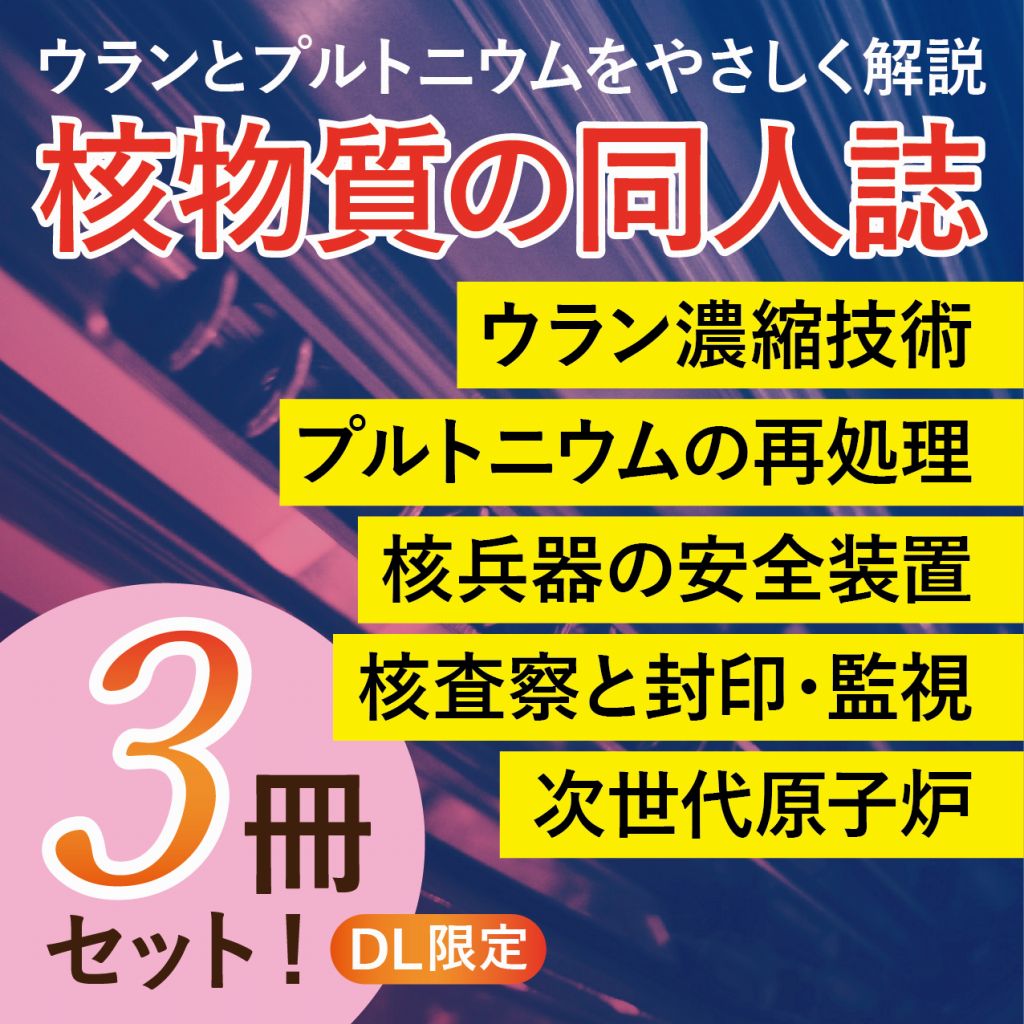プルトニウムやネプツニウムの超伝導体
超電導とは何か?
さてはて「超伝導」といえばリニアモーターカーや粒子加速器などで利用されているものです。そもそも超伝導とは何か、と言うと電気抵抗がゼロになるという現象です。普通のそこら辺にある電線などには電気を通しやすい銅などの金属が使われてますが、どうしても電気抵抗が存在しているのでロスが生じてしまうのです。
通常の物質では、電気を伝える電子はバラバラに動いているような状態であるため、電気抵抗が少なからず存在する状態になってしまうわけです。超低温の環境では電子2個が「クーパー対」というペアを組んで、その物質の電子が全て一緒くたに整った状態(コヒーレントな状態)になります。そのため、抵抗がゼロとなる超電導の状態になるのです。
電子は「フェルミ粒子(フェルミオン)」という種類の粒子なのですが、このタイプの粒子は「パウリの排他律」という制限によって全ての粒子が同じ状態になることができません。そのため、そのままでは全ての電子が同じ状態になるという超伝導は実現できなくなってしまう。しかし、電子がペアになると、そのペアは「ボース粒子(ボソン)」となります。「ボース粒子」は全てが同じ状態になることができるため、ペアとなった電子は全て整った状態になり、超伝導という状態が現れるのです。これが「BCS理論」と呼ばれるものです。
つまり超伝導というのは、量子レベルの現象が物質全体に及ぶという面白い現象なのです。とにかくめちゃくちゃ温度を下げさえすれば超伝導状態になる物質というのはたくさんあるのですが、何度で超伝導になるか、というのは物質によって異なるのです。できればそんなに冷やさなくても超伝導になってくれる物質があれば、様々な面で応用しやすいというメリットがあります。
中には液体窒素よりも高い温度で超伝導になってくれる物質もありますが、実はこれらは前述の「BCS理論」では説明できないものもあるのです。物質の温度が40ケルビンを超えてくると、熱振動という現象によって電子のペアが壊れてしまうためです。そのため、こうした高い温度で超伝導になるという「高温超伝導体」や、有機物によって超電導が起きる「有機超伝導体」は従来の一般的なBCS理論とは異なる理論によって超伝導状態になっている「非従来型超伝導」と呼ばれるものなのです。そして、こうした特徴を持つ超伝導体は「エキゾチック超伝導体」と呼ばれたりしています。
5f軌道の電子のはたらき
ウランをはじめとしたアクチノイド元素においては、5f軌道の電子の存在がその「重い電子系」に分類される超電導状態の発現に関わっています。同様に他のアクチノイド元素であるネプツニウムやプルトニウムについても、その化合物が超伝導転移することがわかっています。
4f電子は原子の内殻に留まっていて局在性が強く、3d電子は動き回っていて遍歴性が強いという特徴がありますが、アクチノイドの5f軌道の電子はそれらの中間的な性質を持つと言われています。この5f軌道の電子はその遍歴性によって重い電子状態でゆっくりと動き回りつつ、局在性によって磁気秩序を示すそうです。これによって重い電子による超伝導状態となりつつ、磁性との共存もできているのです。
また、単体の金属プルトニウムは、室温から融点に至るまでの間に6種類もの結晶構造に次々と変化しますが、これも5f電子が影響しています。
プルトニウム化合物の超伝導体「PuCoGa5」「PuRhGa5」
「PuCoGa5」は、アメリカのロスアラモス国立研究所の実験において、プルトニウム化合物であるPuCoGa5が重い電子系超伝導体としては高い超伝導転移温度を持っていることが発見されました。超伝導転移温度(Tc)は18.5Kと、重い電子系超伝導体としては非常に高いという特徴があります。(それまでは2K程度だったようです。)

「PuCoGa5」の結晶(Image:LLNL)
超伝導体が超電導状態になると、電気抵抗がゼロになるとはいえ、そこに流すことができる電流量には限界があります。これは臨界電流密度と呼ばれています。プルトニウム化合物の場合は、プルトニウム自身のアルファ崩壊によって発生する格子欠陥によって磁束線がピン止めされます。そのため臨界電流密度が高いという特徴も持ちます。つまり超伝導体としてより多くの電流を流せるという優れた性質を持っているため、超電導磁石等に適してはいるのですが、放射性物質であることや、核物質保障措置対象の物質でもあること、また単純に非常に高価であることから実際の利用はかなり困難と考えられます。
また、アルファ崩壊に伴う格子欠陥が生じることで、時間の経過とともに超伝導転移温度を低下させてしまうという事もあります。この点に関してはプルトニウム239ではなく、半減期の長いプルトニウム242を用いれば超伝導転移温度の低下をゆっくりに抑えることができますが、この同位体を単体で精製するのは非常に難しいとされています。
「PuRhGa5」は「PuCoGa5」に次いで発見されたものです。超電導転移温度は8Kと低くなっています。
ネプツニウム化合物の超伝導体「NpPd5Al2」
2007年に日本原子力研究開発機構と2大学の共同研究によって発見された、初のネプツニウム化合物の超伝導体です。超電導転移温度は5Kです。
一般的に超伝導と磁性というのは相性が悪いと言われています。しかし、ネプツニウムとパラジウムとアルミニウムの合金であるNpPd5Al2は磁性体であるにも関わらず、超伝導状態になります。
第二種超伝導体であるため、完全な超伝導状態から超電導と常電導が入り混じった渦糸状態となる「下部臨界磁場(Tc1)」と、渦糸状態から完全に常伝導状態となる「上部臨界磁場(Tc2)」を持ちますが、磁場の強さが上部臨界磁場に近づいていくと、この化合物が磁化の大きさが増大する(通常は小さくなる)という変わった特徴も持つそうです。