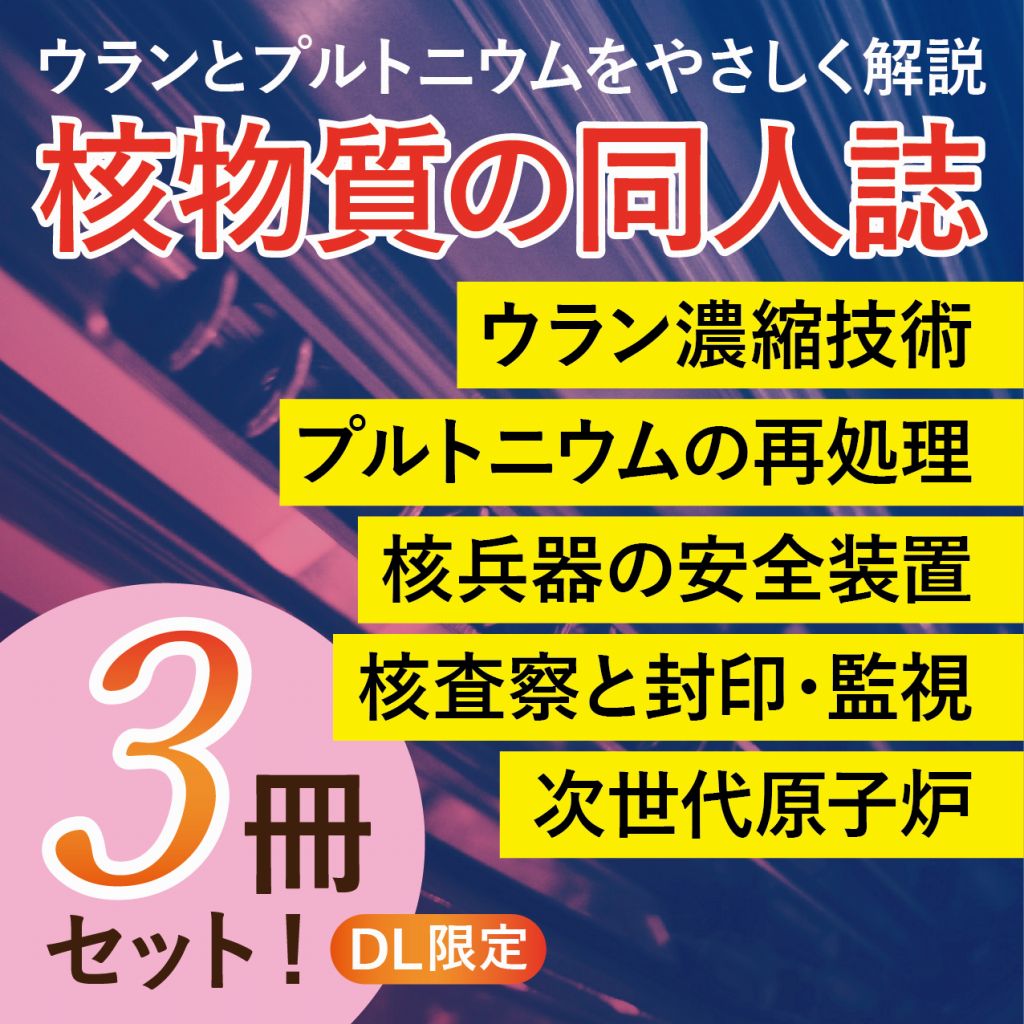水素爆弾の構造と起爆過程
熱核兵器(水素爆弾)のしくみ
熱核兵器の構造
熱核兵器は水素爆弾とも呼ばれていますが、熱エネルギーにより核融合反応を引き起こすことから熱核兵器と呼ばれています。核融合を引き起こすためのエネルギー源としては核分裂エネルギーが主に用いられ、段階的にその反応が引き起こされることから多段式核兵器とも呼ばれています。最初の核分裂エネルギーをもたらす部分は言わば原子爆弾そのものです。これは「プライマリ」と呼ばれており、ここで高濃縮ウランや兵器級プルトニウムが爆縮レンズと呼ばれる圧縮機構によって核分裂連鎖反応が一気に引き起こされます。その際に生じるエネルギーが「セカンダリ」と呼ばれる部分で核融合反応を引き起こし、最終的に大きな威力を生み出すというものです。熱核兵器は大きなものでTNT換算でメガトン級の威力を持ちます。1メガトンは1000キロトンであり、これはつまり高性能爆薬であるTNTに例えるならば100万トン分の威力があるということになります。
プライマリ(原子爆弾)の起爆
熱核兵器において、原子爆弾であるプライマリには、核分裂性物質に高濃縮ウランまたは兵器級プルトニウムを用いたインプロージョン(爆縮)型が多く使用されています。インプロージョン型とは球体の核分裂性物質包み込む爆縮レンズと呼ばれる装置を用い、爆薬を使用して周囲から一気に圧縮することで核分裂連鎖反応を開始させるタイプの原子爆弾です。爆縮レンズは燃焼速度の異なる二種類の爆薬を用うことで、爆発波をコントロールし、中心部のピットと呼ばれる核分裂性物質を均一かつ正確に圧縮することができます。爆縮レンズが作動することで一気に爆縮されたピットでは核分裂連鎖反応が開始されますが、これは「即発臨界」と呼ばれる核分裂の連鎖反応が極めて短時間で増大する状態となります。核分裂連鎖反応を進み具合を示す「反応度」をごく短時間ながら維持することで、瞬間的に爆発的な熱エネルギーの放出が行われます。この時プライマリは極めて高い温度になりますので、「黒体放射」によってX線が放出されることになりますが、これがセカンダリ部分を作動させるのに重要な役割を果たします。
核融合によるブースト型核分裂兵器
基本的な原子爆弾では核分裂連鎖反応によって大きな威力をもたらしますが、近年の原子爆弾においては核融合反応を併用したブースト型核分裂兵器(ブースト型原子爆弾)が多く採用されています。これは原子爆弾において中心部の核分裂性物質の中心部に空洞を設け、そこに重水素とトリチウムのガスを充填し、原子爆弾の起爆時の核分裂連鎖反応による高温高圧の環境を利用して核融合反応を引き起こすというものです。この際の核融合反応は水素爆弾とも呼ばれるような熱核兵器とは異なり、核爆発の威力に直接大きくは影響しません。重要なのはその核融合の際に生じる大量の中性子であり、この中性子によって核分裂性物質をより効率的に核分裂させられます。
重水素とトリチウムの混合ガスは起爆直前にガス・リザーバーと呼ばれる容器から注入されます。最初から核分裂性物質の中心部に充填しておかないのはトリチウムに寿命があるためです。トリチウムの半減期は約12.3年であり、長期間保管しておくと放射性崩壊によってどんどん失われてしまいます。さらにトリチウムの崩壊で生じるヘリウム3は中性子を吸収しやすい性質を持つため、核分裂反応を強化するどころかむしろ邪魔になってしまう場合もあります。そのためガスは定期的に充填しなおすことができるように起爆直前までガス・リザーバーに保管してあるのです。
こうした核融合の利用による核分裂の強化を行った初の核実験は、1951年5月にアメリカが行った「グリーンハウス作戦」の「ジョージ実験」で使われた「シリンダー」と呼ばれる核爆発装置によって行われました。核融合が初めて核爆発に用いられた実験であり、名前通りの円筒形の核爆発装置の中心部分に、極低温の液体重水素と数パーセントの液体トリチウムによる混合液のタンクが設置されていました。核融合による直接の威力は当初想定されていたよりも僅かであったものの、核融合によって生じた中性子によって核分裂が促進されることになりました。また、この円筒形の核爆発装置はあくまでも核実験用であり、兵器としての実用化は考えられていませんでした。このジョージ実験に続いて行われた「アイテム実験」により、ガス状のトリチウムと重水素を用いたブースト型原子爆弾の初実験が行われました。
初めてこうしたブースト型原子爆弾が実用核兵器として利用されたのは艦載用の対空ミサイルRIM-8「タロス」用のW33核弾頭です。主に爆撃機などの大型航空機に対して使用される長距離艦対空ミサイルであり、中には核弾頭を搭載することで敵爆撃機編隊を一網打尽に迎撃しようとしたものがありました。そこに搭載されたW33核弾頭は非常に小型であったため、十分な核出力を得られるようにブースト型原子爆弾としての設計が利用されました。
核融合を核兵器として利用しようとするアイデアは昔からありましたが、当初は原子爆弾のすぐ隣に液体重水素を設置すれば、十分な核融合反応が生じ、そこから直接兵器としての威力が得られるであろうと考えられていました。これは「クラシカル・スーパー型」と呼ばれていました。しかしこれはブースト型原子爆弾として機能するのみで、実際に核融合は発生するのものの、その規模は小さく核分裂を強化する程度で核融合そのものから莫大な威力を直接得ることはできませんでした。核融合反応を大きく引き起こす完全な熱核兵器は後述する「テラー・ウラム型」と呼ばれるものとして完成しました。
原子炉級プルトニウムとブースト型原子爆弾
核兵器に使用されるプルトニウムは兵器級プルトニウムと呼ばれているのに対し、原子力発電所の核燃料として使用されるプルトニウムは原子炉級プルトニウムと呼ばれています。原子炉級プルトニウムはプルトニウム同位体比率のうち、プルトニウム238やプルトニウム240の割合が大きくなっています。これらのプルトニウム同位体は自発核分裂(Spontaneous Fission)と呼ばれる現象を起こしやすいという特徴を持っています。自発核分裂とは放射性崩壊のように一定の割合で自然に引き起こされる核分裂です。原子爆弾においてこうした同位体が多すぎると起爆時に爆縮レンズによる爆縮がまだ不十分な状態から核分裂連鎖反応が開始されてしまい、不十分な核爆発となる「不完全核爆発(Fizzle)」の原因となります。
不完全核爆発では威力はTNT換算で数キロトン程度にまで低下します。さらにこれらの同位体は半減期が短いという特徴があり、そのぶん単位時間あたりに出す放射線の量が多く、爆弾の組み立て時や維持・管理においても作業者の被曝線量が大きくなってしまいます。さらに放射線量が多いということは、単位時間あたりの崩壊熱も大きくなってしまいます。つまり爆発前から爆弾が勝手に加熱されてしまうということになり、その放熱が十分になされない場合には爆縮レンズに用いられる爆薬の劣化や起爆用機器の故障等を招く可能性もあります。
そのため原子炉級プルトニウムは核兵器には不適なのですが全く利用できないわけではなく、前述のとおり威力が数キロトン程度の不完全核爆発でも構わなければ核兵器として利用できるとも考えられます。数キロトンとは言え通常爆薬と比較すると大きな威力を生じさせますし、起爆時の放射線や放射性降下物による影響も生じます。また原子炉級プルトニウムで原子爆弾を製造する際に、前述のブースト型原子爆弾の設計を利用した場合、不完全核爆発であっても十分な核融合反応を引き起こせるだけの条件を達成できれば、威力をある程度強化することも可能であると考えられます。
但し、兵器級プルトニウムと比較して威力が劣る上に取り扱いの難しい原子炉級プルトニウムを核兵器に利用できるだけの技術があるのであれば、そもそも兵器級プルトニウムを生産できるだけの設備と技術も揃っていると考えられますし、最初から兵器級プルトニウムを利用した方が様々な点において有利です。また、ブースト型原子爆弾に使用するトリチウムも生産するには原子炉でリチウムに中性子を照射する必要があります。つまり必要となる設備の点でも原子炉級プルトニウムを核兵器に利用する利点は無く、そうした点からも核兵器には不適であると考えられます。
放射爆縮と熱核兵器
「プライマリ」の核分裂エネルギーを「セカンダリ」へと適切に転送するための技術として、間接照射型の慣性核融合と同じように爆弾の外殻となる空洞部分(ホーラム)からの黒体放射を利用した軟X線が利用されます。これは放射爆縮(Radiation Implosion)と呼ばれており、言わば原子爆弾であるプライマリをエネルギードライバーとした一種の間接照射型の慣性閉じ込め核融合システムと言えます。
この放射爆縮を利用したものが水素爆弾とも呼ばれる熱核兵器そのものであり、テラー・ウラム型とも呼ばれています。テラー・ウラム型は開発者で「水爆の父」とも呼ばれたエドワード・テラー博士と、スタニスワフ・ウラム博士の名前をとって付けられました。
セカンダリの放射爆縮は、プライマリの起爆に利用された化学爆薬による爆縮レンズを遥かに凌ぐエネルギーが利用されます。まず、プライマリが起爆した際に熱核兵器の内部が急激に超高温に加熱され、放出された軟X線が内部で放射と吸収を繰り返し、内部はその軟X線でによって均質に満たされる事になります。これは黒体放射と呼ばれ、プライマリを均質かつ正確に爆縮するために非常に重要なものとなります。前述の「クラシカル・スーパー」方式ではこの軟X線の黒体放射による正確な爆縮を利用せず、原子爆弾からの熱エネルギーをそのまま重水素に直接照射するだけのものであったため、十分な核融合による威力を得るに至りませんでした。
テラー・ウラム型においてセカンダリを放射爆縮するエネルギーの多くはセカンダリの外側を覆うウラン等の重元素が、軟X線の照射によって瞬間的に加熱され、外側に向かって急激に気化する際に内側に向かって圧縮されます。この作用・反作用のロケット効果による「アブレーション(Ablation)」という現象がセカンダリの爆縮に利用されています。このアブレーション圧力によりプライマリが爆縮されるのです。
核融合点火
放射爆縮によりセカンダリの核融合燃料が圧縮されると高温高圧の状態になります。しかしこれだけでは核融合反応を生じさせるには十分な圧力を得るのは難しいため「スパークプラグ」と呼ばれるものを利用しています。スパークプラグはセカンダリの中心部に設置されており、高濃縮ウラン、もしくは兵器級プルトニウムで構成されています。これがセカンダリの爆縮に伴って圧縮されることで超臨界状態となります。超臨界状態となったスパークプラグにより核融合点火が可能な温度と圧力が生み出されます。
この直前、プライマリからの中性子による予熱問題をできるだけ回避する必要があります。予熱(プレヒート)とはセカンダリにおいて核融合点火が起きる前に、プライマリの熱放射や中性子による加熱が生じる状態を指します。セカンダリが予熱されてしまうと熱膨張により、放射爆縮の妨げとなってしまいます。そのためプライマリの熱放射や中性子の影響を最小限に抑えるよう、プライマリとセカンダリが直接向かい合う部分にはウランなどが設置されています。つまりセカンダリが放射爆縮される直前までは、セカンダリに照射される中性子の量を最小限に抑えておかなければならないのです。
核変換
重水素化リチウム(LiD:Lithium Deuteride)に含まれる重水素がD-D反応によって中性子を生じさせ、その中性子を吸収したリチウムが核変換によってトリチウムへと変化します。これによってD-T反応に必要な燃料がその場で生成されることになります。D-T反応はD-D反応よりも反応条件が易しいため、この時点からD-T反応によるエネルギーと中性子の放出が支配的なものとなります。そしてこの時放出された大量の中性子が、爆弾の外殻部分に配置されたウラン238等の核分裂可能な物質に照射されることで核分裂反応を発生させ、さらなるエネルギー放出が引き起こされることになります。ウラン238は単体では核分裂の連鎖反応を維持することはできませんが、外部から高エネルギーの中性子(高速中性子)が入射される事により、核分裂反応を起こすことができます。D-T反応で生じる中性子は14MeVという非常に高いエネルギーを持っているためにこれが可能となり、これによって莫大な破壊的エネルギーの放出が可能になります。
熱核兵器が炸裂するまで
テラー・ウラム型と呼ばれる熱核兵器が起爆し、炸裂するまでのごくわずかな一瞬の間に何が起きるのかを順に追ってみましょう。
①プライマリの起爆
まず原子爆弾であるプライマリが爆縮レンズの動作によって起爆します。高濃縮ウランや兵器級プルトニウムのピットが爆縮された最適なタイミングで、重水素とトリチウムのDT反応による中性子を利用した外部中性子源(ENS)が作動し、超臨界状態で核分裂連鎖反応が開始されます。外部中性子源はトリチウムを吸蔵させた金属に対して、小型静電加速器を用いて重水素イオンを照射することで中性子を生み出します。
②核融合ブーストによる核分裂増大
プライマリが起爆する際、ピットの中心部には重水素とトリチウムの混合ガスがガス・リザーバより充填されているため、超臨界状態となったプライマリの高温高圧の環境下でトリチウムと重水素の混合ガスの核融合反応が引き起こされます。この時に生じる高速中性子が核分裂性物質の核分裂反応をさらに促進させていきます。
③放射爆縮とセカンダリの起爆
核分裂反応によって爆弾の外殻部が超高温に加熱されることにより、X線の黒体放射が生じます。X線は吸収と放出の繰り返しにより外殻の内部を均質に満たします。その均質なX線によりセカンダリが爆縮されると同時に、セカンダリ中心部のスパークプラグと呼ばれる核分裂性物質の円筒が超臨界状態となります。放射爆縮されたセカンダリは、スパークプラグによってさらに高温高圧の状態となります。
④スパークプラグとDD核反応の開始
核融合反応においてDD反応は反応条件はDT反応よりも厳しいものの、重水素のみで核反応が起こせるのが特徴です。そのためセカンダリの爆縮とスパークプラグの超臨界状態による高温高圧の状態になった重水素化リチウムにおいてDD反応が最初に点火され、核融合燃焼が開始されます。
⑤核変換
X線による放射爆縮とスパークプラグでDD反応の核融合点火が生じると大量の中性子が生成されることになります。これによりリチウムからトリチウムが生成される核変換が生じます。
⑥核融合反応の増大
リチウムからトリチウムが生成されると、重水素との核融合反応であるDT反応が生じます。このタイミングからDD反応よりも反応を起こしやすいDT反応が、放出される核融合エネルギーの大部分を占めるようになります。
⑦高速中性子による第三段階の核分裂
DD反応やDT反応によって生じた大量の高速中性子は爆弾の外側へ向かって大量に放出されます。この時、爆弾の外殻がウラン238で構成されていた場合、高速中性子による核分裂が生じます。ウラン238は天然に存在するウラン同位体の大半を占める核分裂しにくい物質ですが、高速中性子では核分裂を引き起こしやすくなります。この第三段階により威力が大幅に向上し、熱核兵器の威力の大部分はこの第三段階が占めているとされます。