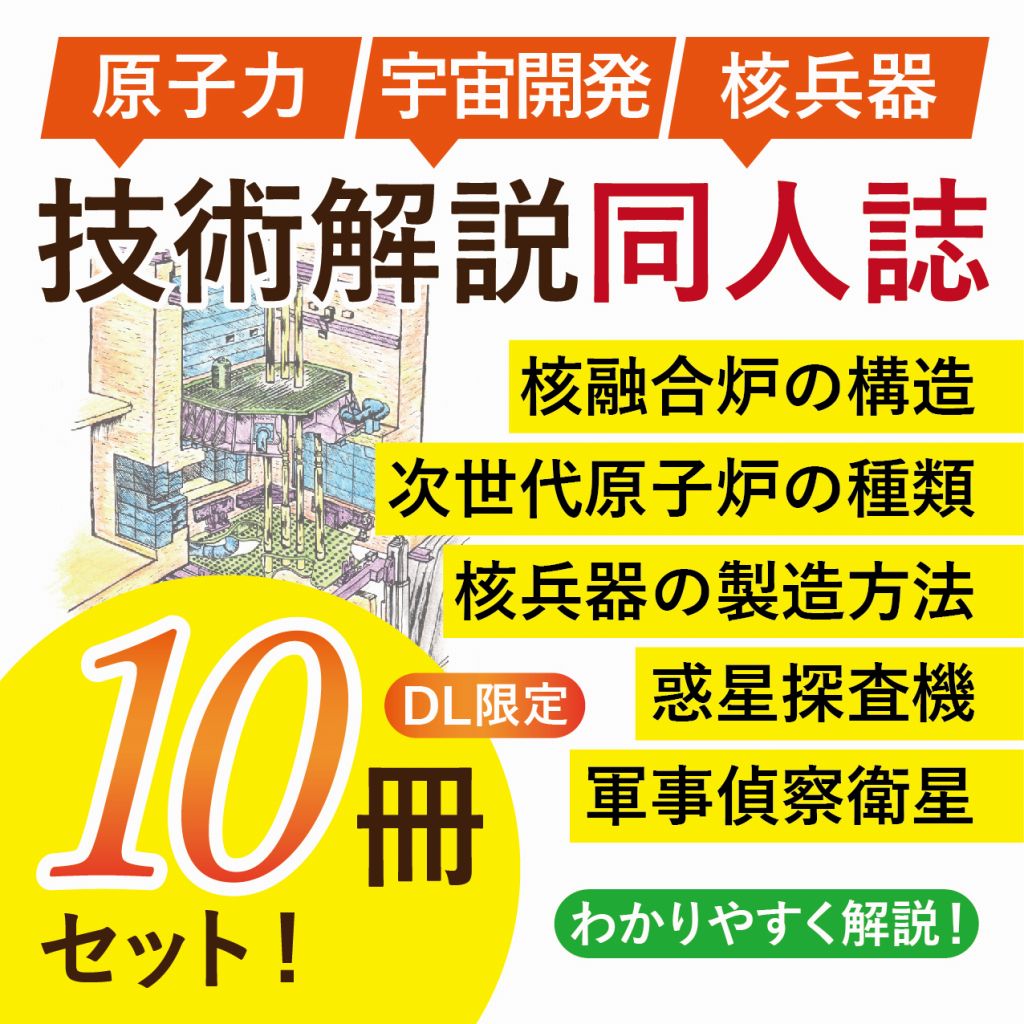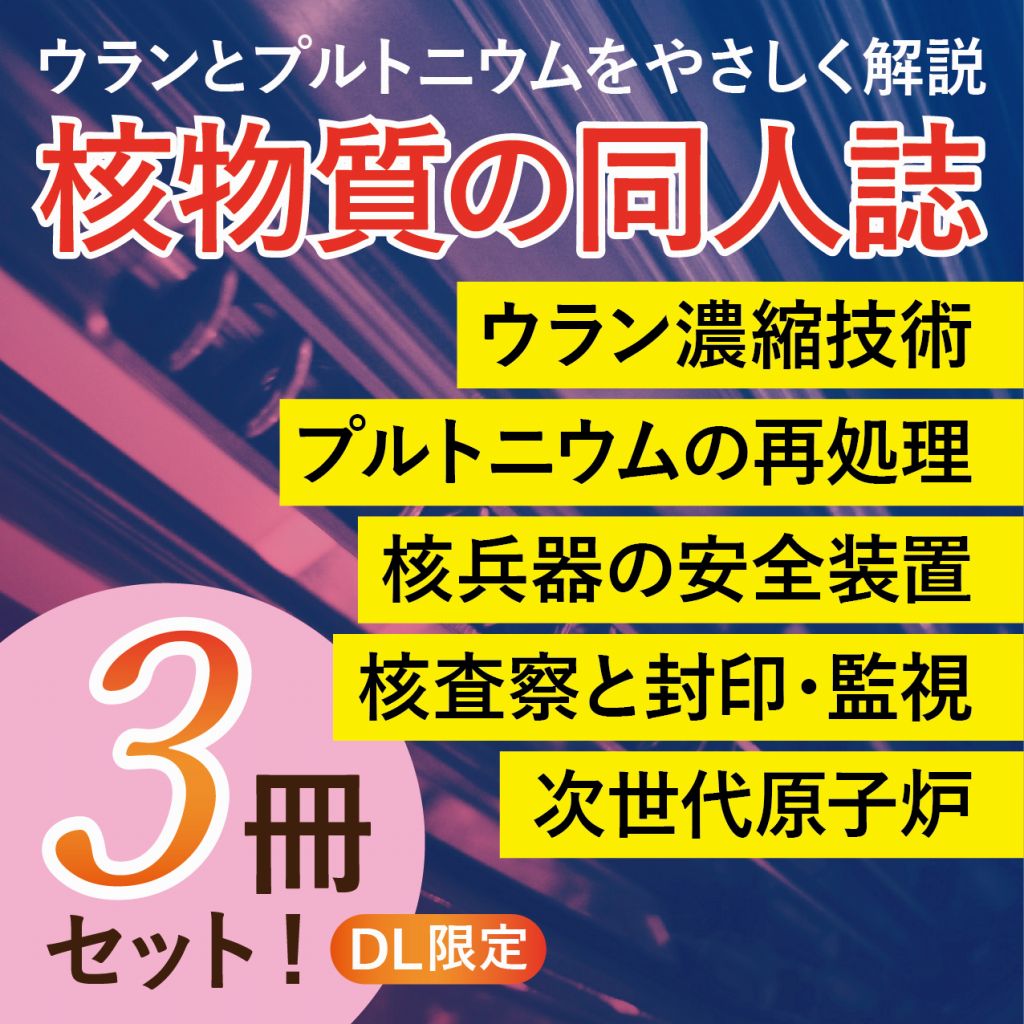核融合炉の特徴と安全性
暴走しない
核融合炉では、核分裂炉における反応度事故(核分裂の連鎖反応が異常に進行する状態)のような出力暴走事故が原理的に起こりえません。核分裂炉ではそうした事故が起きないように炉心が設計されていますが、核融合炉ではそうした配慮は不要になります。核融合反応は高温・高密度のプラズマを必要とするため、何らかの理由で通常運転状態ではなくなってしまうとプラズマが維持できなくなり、自然に核融合反応が停止するためです。また、停止させる場合もプラズマを維持するための機器の電源を切断すれば核融合炉はその瞬間に停止することになります。
放射性廃棄物が少ない
核分裂炉の場合はウランやプルトニウムといった核分裂性物質が中性子によって核分裂した時に生じる核分裂生成物や、中性子を吸収してより重い元素へと変換されたりすることによって生じるマイナーアクチノイドと呼ばれる元素により、強い放射能を持つ高レベル放射性廃棄物(HLW:High Level Waste)が生じます。これらは核燃料サイクルによって分離したり、核変換と呼ばれる技術でさらに別の元素へと変換することでその量を大幅に減らし、地層処分することなどが考えられています。
核融合炉の場合はそれらのウランやプルトニウムといった核分裂性物質を用いないため、そうした高レベル放射性廃棄物が生じないという特徴があります。核融合を構成する材料が、核融合の際に生じる中性子を吸収することで放射性物質に変換されることはありますが、50年程度保管することによってその放射線量は低下し、低レベル放射性廃棄物(LLW:Low Level Waste)として処分できます。
放射化材料とトリチウム
核融合炉の安全管理の上で重要になるのが、放射化材料と呼ばれる中性子によって放射能を持った核融合炉の構成材料と、核融合燃料となるトリチウムの取り扱いです。放射化材料のうち、特に核融合を引き起こすためのプラズマの近くにあるものはそのプラズマの影響によって小さな粒子となって核融合炉外へ放出されないように管理されます。これらはプラズマそのものに対しても不純物として影響してしまうため、磁場閉じ込め方式の核融合炉の場合はダイバータと呼ばれる装置で排出されるようになっています。
また、核融合の燃料となるトリチウムは放射性であるため、施設外に大量に漏洩したりしないように管理する必要があります。一方でトリチウムが出す放射線は弱いベータ線であり、これはよほど大量でなければ環境や人体に対して大きな影響を及ぼすことはありません。トリチウムは核融合炉のブランケットと呼ばれる外壁部分でリチウムを原料として、中性子を吸収させることで生産されます。核融合炉で生産されたトリチウムは精製され、核融合炉の燃料として供給されることになります。つまり作られたトリチウムはそのまま燃料として消費されるという循環をするため、核融合炉のシステム全体の中で存在するトリチウムは重量にして数キログラム程度で済みます。