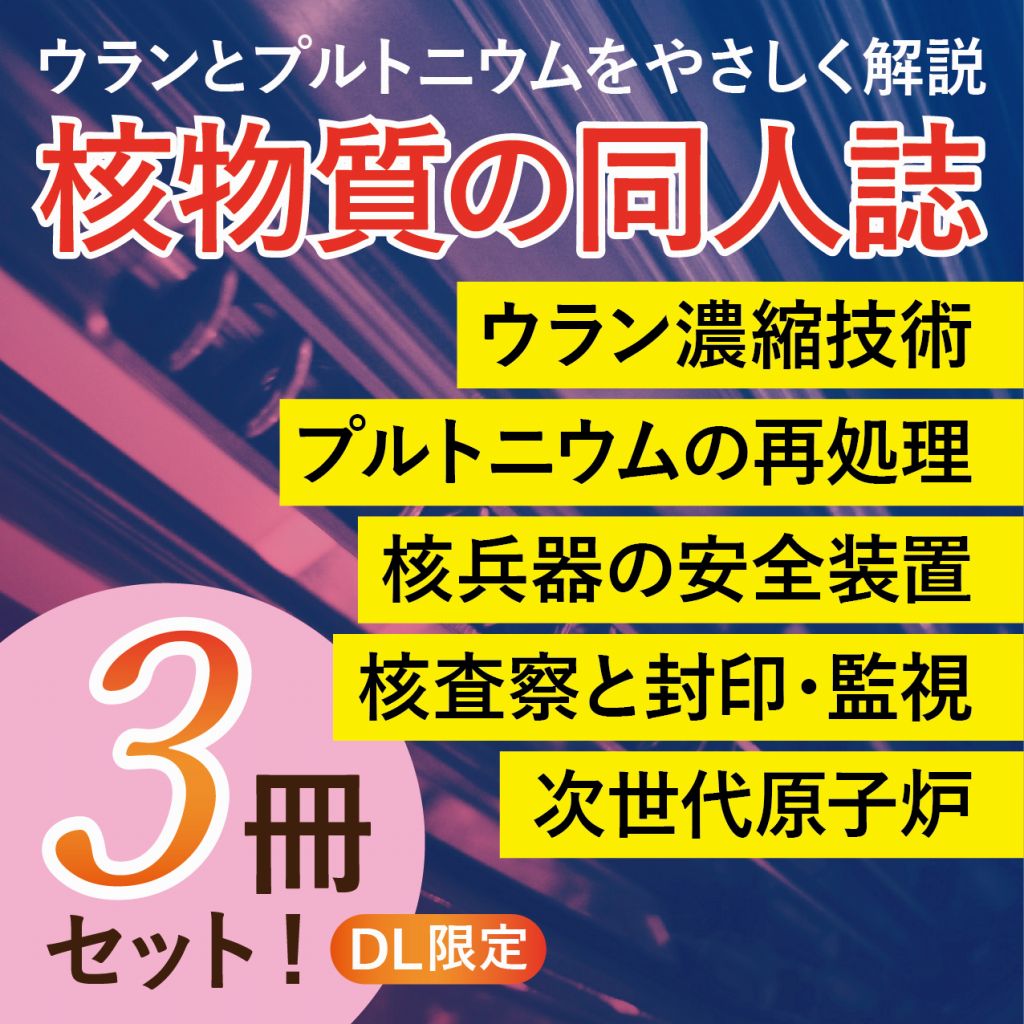高速増殖炉とは
高速増殖炉のしくみ
原子炉とはウランやプルトニウムといった核燃料となる物質、核分裂性物質の核分裂連鎖反応を安定的に持続させるためのシステムです。核分裂性物質の原子核に中性子が当たると一定の確率で核分裂を引き起こします。そしてその核分裂の際に新たな中性子が2個から3個同時に放出され、この中性子がさらに次の核分裂を引き起こすという連鎖反応を維持します。
この状態を「臨界」と呼び、原子炉では核分裂が一定して連鎖するよう、臨界を制御できる構造になっています。原子炉と一口に言っても様々な種類があります。現在、世界の原子力発電所で最も多く利用されている原子炉は軽水炉(LWR)と呼ばれるタイプのものです。沸騰水型軽水炉(BWR)と加圧水型軽水炉(PWR)の二種類があり、普通の水である軽水を原子炉を冷やすための冷却材として利用し、また核分裂連鎖反応を起こしやすくする減速材としても利用するタイプの原子炉です。
減速材は中性子の運動エネルギーを遅くするためのものです。核分裂で生まれた中性子はそのままの状態ですと速度が速く、大きな運動エネルギーを持った状態にあります。中性子はその速度が速すぎると、池に向かって思いっきり投げた小石のように原子核に当たっても吸収されにくく、結果として核分裂を起こす確率が低くなります。そのためほとんどの原子炉では減速材を用いて中性子の速度を落とし、核分裂が起きやすくしているのです。
このように速度を落とした中性子の事を熱中性子と呼び、この熱中性子を利用する原子炉は熱中性子炉と呼ばれます。 軽水炉で冷却材と減速材を兼ねて利用される軽水は身近な普通の水であるためコストも安いのですが、軽水はそれ自身が中性子を吸収し、捕獲してしまう(食いつぶしてしまう)吸収断面積が比較的大きくあります。
つまり核分裂を効率よく引き起こすためにある減速材ですが、その減速材自身が核分裂の連鎖反応に必要な中性子を吸収してしまうということです。そのため、核燃料であるウラン235の含有率が0.7パーセント程度の「天然ウラン」では臨界を実現するのは難しいため、その割合を3パーセント程度まで増やした「低濃縮ウラン」が利用されています。こうすることで容積あたりの核分裂性物質の割合が増え、中性子が核分裂性物質の原子核に当たりやすくなり、臨界を維持できます。
また、軽水炉の他にも重水や黒鉛(グラファイト)を減速材に用いる重水炉(HWR)や黒鉛炉(GMR)といった原子炉があります。重水や黒鉛は、軽水よりも中性子を吸収してしまう確率が低いため、核燃料を濃縮せずとも天然ウランのまま利用できるという特徴があります。これらの熱中性子炉が減速材を用いて中性子を減速し、臨界を維持しているのに対して中性子を減速させずに核分裂で生じた高速中性子をそのまま利用する原子炉の事を高速中性子炉、高速炉(FR)と呼びます。
さらにこの高速炉のうち、核燃料を使った量以上に増やすこと、つまり増殖ができる原子炉の事を高速増殖炉(FBR)と呼びます。高速炉(FR)と高速増殖炉(FBR)の違いは核燃料の増殖を目的としているかどうか、ということになります。高速中性子を使う事により、核燃料として利用されるプルトニウムが核分裂する確率よりも、ウランからプルトニウムが作られる確率の方が大きくなります。
これが増殖であり、使った以上の燃料を生産することができるのです。さらに高速炉においてはこうした燃料の生産以外にも様々な利点が存在します。減速材を用いない高速増殖炉では核燃料の間隔が狭くなり、容積あたりの出力は熱中性子炉よりも大きくなります。そのため原子炉で生じた熱を冷却し、輸送するためにはこれまでの水では冷却能力に限界があり、また水自体が中性子を減速させてしまうため高速増殖炉の冷却材として利用するのは難しくあります。そのため、水よりも冷却能力に優れ、中性子を減速させづらいナトリウムや鉛、ビスマス、リチウムといった液体金属が利用されます。
高速増殖炉のメリット
核燃料の増殖
高速中性子を利用して実現できる、核燃料を「使った以上に増やせる」高速増殖炉の仕組みとはどういうものなのでしょうか。核燃料に含まれるウランには主に核分裂性のウラン235と、核分裂性でないウラン238が存在しています。ウラン238は中性子を吸収すると2回のベータ崩壊を経て核分裂性のプルトニウム239へと変化する性質があります。
軽水炉などの熱中性子炉においてはウラン235が核分裂する割合に対して、ウラン238がプルトニウム239に変化する割合が0.3 ~ 0.6倍ほどあります。これは「転換」と呼ばれ、その比率は「転換比」と呼ばれます。こうして原子炉内で作り出されたプルトニウム239も核分裂することで発電に役立っています。
また使用済み核燃料にも含まれるため再処理により取り出す事ができ、再び核燃料としてリサイクルできます。高速増殖炉では高速中性子を利用することによって、プルトニウム239が中性子により核分裂する確率よりも、ウラン238が中性子を吸収してプルトニウム239に変化する確率の方が高くなるため、結果としてプルトニウムが燃焼するよりも多くプルトニウムを作ることができるのです。
また、核分裂性物質が核分裂を起こした際に放出される中性子の平均数は、入射した中性子のエネルギーが高いほど多くなるため、核燃料の増殖という点においてプルトニウムを核燃料とし、高速中性子を用いる高速増殖炉は有利なのです。
高速増殖炉においては燃やした燃料に対して、転換によって生産できた燃料の方が多くなるため、この割合を示す値は「転換比」ではなく「増殖比」と呼んでいます。「もんじゅ」の場合はこの値が1.2であり、これは薪を10本燃やすと新たに薪が12本出来ている暖炉のようなものです。
また、増殖比を上げるにはMOX燃料中のプルトニウム239の割合(富化度)を下げ、ウラン238の割合を上げることなどで達成できます。この増殖により核燃料をより効率的に利用でき、高速増殖炉による核燃料増殖によって数千年にわたるエネルギー供給が可能になると考えられています。
ウラン濃縮不要
高速増殖炉においてはMOX燃料と呼ばれるプルトニウムを主体とした核燃料を利用するため、従来の軽水炉などで必要だったウラン235の濃縮が不要になるというメリットがあります。従来の軽水炉などで用いられる核燃料においては、天然のウランに0.7パーセント程含まれる核分裂性のウラン235を3パーセント程まで増やす必要があるため、濃縮という工程が必要となります。
これは同じウランの同位体のうち、質量の軽いウラン235を、全体のほとんどを占めるウラン238との重さの違いを利用して取り出す事で行われます。しかしプルトニウムを利用するMOX燃料の場合は、天然ウランよりもウラン235が少ない劣化ウランにプルトニウムを混合して作られるため、濃縮の工程が不要となります。
高燃焼度の達成
高速増殖炉では運転しながら燃料を増やす事ができるため、炉心に装荷した核燃料においても核分裂性のプルトニウムが核分裂しつつ、ウラン238もプルトニウム239へと変わっていきます。そのため核燃料が自己補充されることになるため、軽水炉の約40,000MWd/t程度の燃焼度に対し、高速増殖炉では約100,000MWd/t程度まで燃やすことができます。
MWd/tは燃焼度と呼ばれ、1トンあたりの核燃料が使い終わるまでの間にどれだけの熱エネルギーをもたらしたかを、1日間で発生した熱出力の総発熱量で表した数値です。この数字が多ければ大きいほど、原子炉で長期間沢山の熱エネルギーを生み出した事になります。燃料集合体あたりの燃焼度を高くすることで取り出せるエネルギーの量を増やし、核燃料を効率良く利用することができます。
放射性廃棄物の核変換処理
原子炉でウランが中性子を吸収し、ベータ崩壊を経て生成される物質にはプルトニウム以外にネプツニウムやアメリシウム、キュリウムといったマイナーアクチノイド(MA)と呼ばれる超ウラン元素も含まれます。プルトニウム239やウラン235などは核分裂しやすい物質ですが、一定の確率で核分裂を起こさずに中性子を吸収してこうした重い元素を生成します。
これらの元素はプルトニウムと違い、熱中性子炉の熱中性子では核分裂を引き起こしにくく、原子炉内の中性子を無駄に吸収してしまう確率も大きい元素です。そのため核燃料サイクルにおいてはこれらの超ウラン元素は分離され、放射性廃棄物として処理されます。
これらの超ウラン元素は高速中性子によって核分裂を引き起こす確率、核分裂断面積が大きくなるという性質を持っているものが多くあります。高速中性子を用いる高速増殖炉においては、これらの超ウラン元素を核燃料と一緒に装荷しておくことで、核燃料として核分裂させてしまうことができます。
これは半減期が長く、長期間の保管が必要な超ウラン元素を核燃料として燃焼させつつ、半減期の短い核分裂生成物に変えてしまえるという利点を持ちます。放射性廃棄物を減らし、また燃料としても利用できるのは高速炉・高速増殖炉の大きなメリットです。
高い熱効率の実現
「もんじゅ」をはじめとした高速増殖炉の多くは冷却材に液体金属であるナトリウムを利用しています。ナトリウムは水と比較して熱を輸送する能力が高いため、軽水炉では300℃程度だった冷却材の温度を500℃近くまで高められ、容積あたりの熱効率が良くなります。
軽水炉では生み出された熱エネルギーの30%~ 35%程度が電気エネルギーとして取り出せていましたが、高速増殖炉では40%以上までその効率を高められます。これまでの軽水炉では熱効率を上げるため、本来1気圧では100℃で沸騰する水を300℃程度で沸騰させられるよう、原子炉を圧力容器で70 ~ 150気圧まで加圧していました。
しかしナトリウムの場合は1気圧での沸騰温度が800℃程度であるため、原子炉を加圧する必要がなく常圧での運転が可能です。これにより軽水炉のような極めて高い圧力に耐える頑丈な圧力容器が不要となり原子炉容器を薄くできるほか、原子炉の意図しない減圧によって冷却材が沸騰し、急激に失われる冷却材喪失事故(LOCA)が原理的に大変起きづらくなっています。
また、前述の通りナトリウムは熱輸送能力に優れるため、原子炉が電源を失った場合でも自然循環で冷却を続けられるという安全性に優れたメリットもあります。