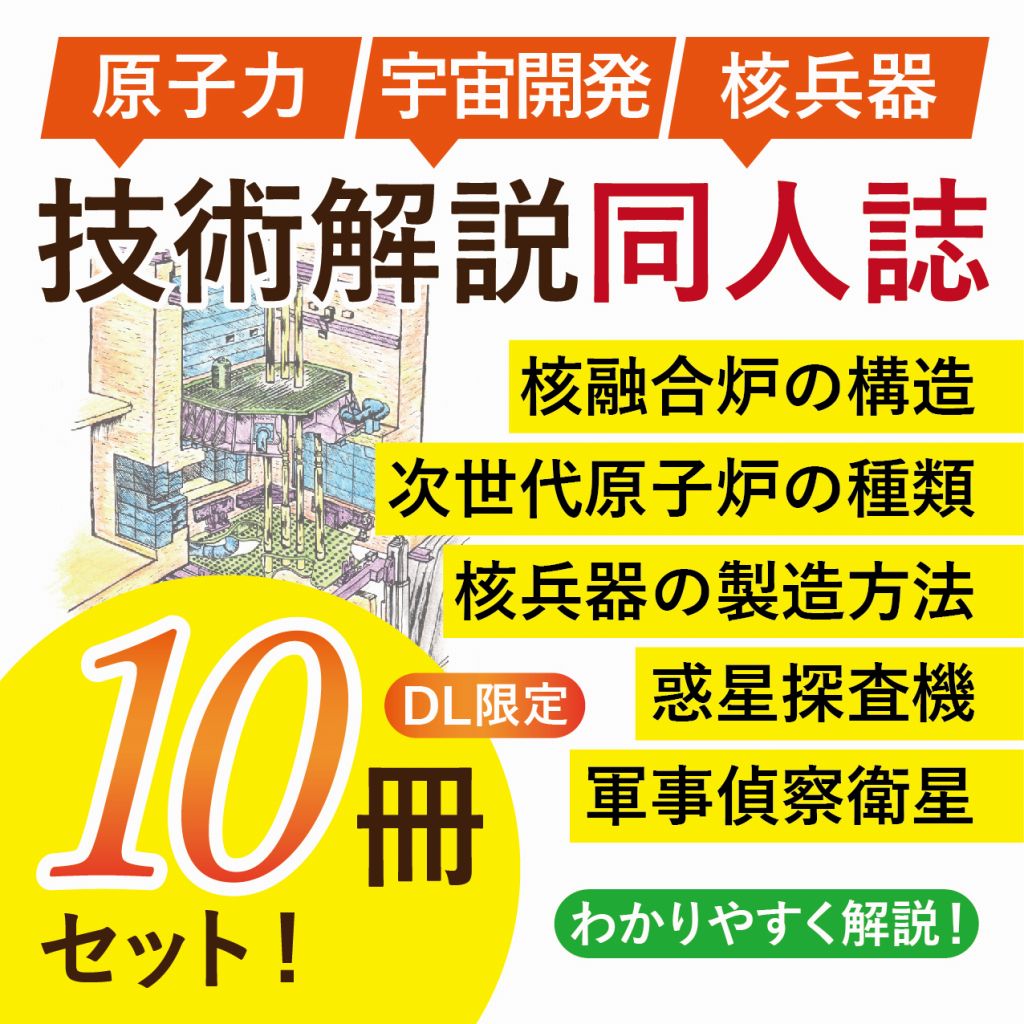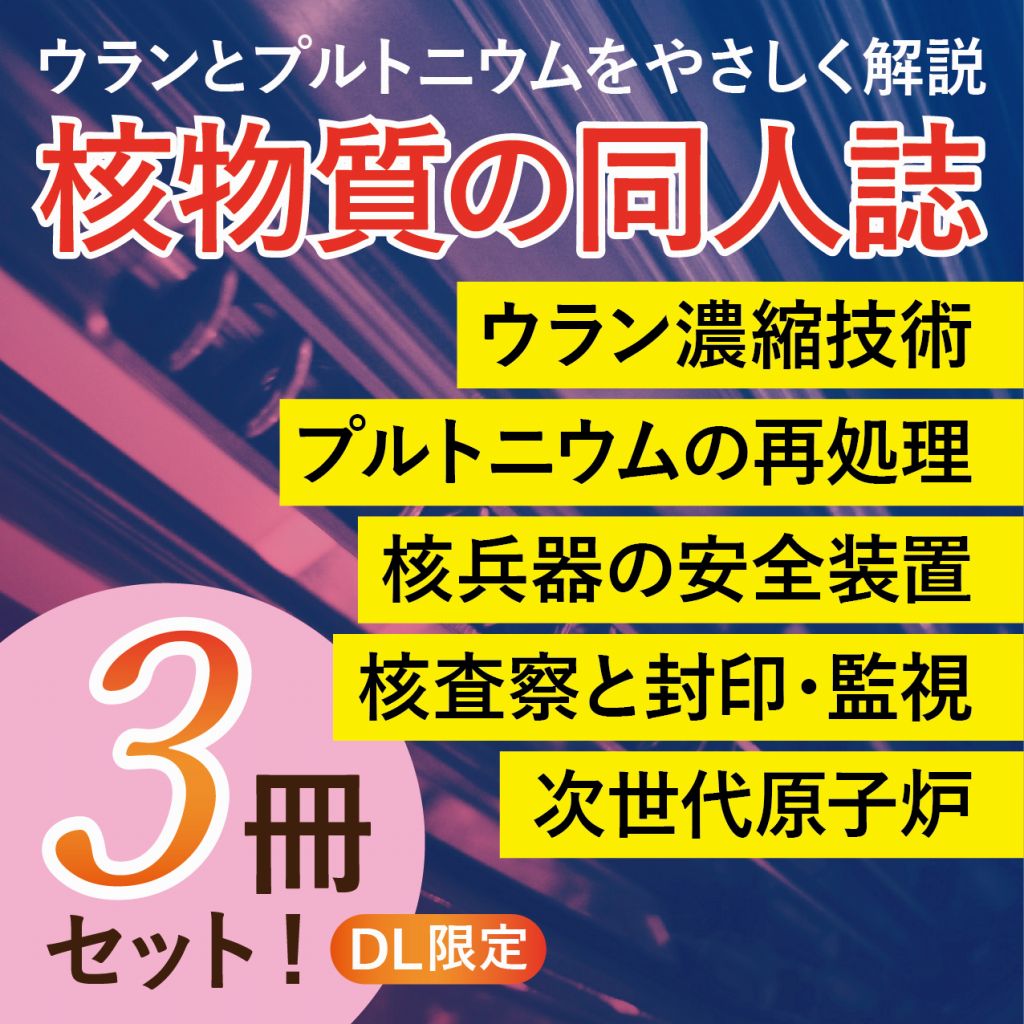原子炉の種類(用途別)
原子炉というのは、ウランやプルトニウムといった核分裂性物質の、核分裂連鎖反応を安定的に発生させる装置のことを言います。核分裂反応が起きると
- 熱エネルギー
- 放射線(ガンマ線や中性子線など)
熱源としての原子炉
原子炉で発生させた熱を何に使うかと言えば、発電や推進力への利用が挙げられます。
発電用原子炉
要するに原子力発電所の原子炉がこれになります。原子炉で発生させた熱を何らかの形で電気に変える事で、電源として利用するというものです。原子力発電所では核分裂で生じた熱エネルギーで蒸気を発生させ、その蒸気を用いてタービンを回し、発電機を駆動させるという「汽力発電」を行います。熱で蒸気を発生させるという点では火力発電と似ています。
ちなみに現行の原子力発電所では、発生させた熱エネルギーに対して生み出せる電気エネルギーは30パーセント程です。
熱エネルギーを直接的に電力に変換する方法としては、
- 半導体素子を用いたゼーベック効果による温度差発電
- 熱電子放出を利用した熱電子発電
- スターリングエンジンを用いた発電
が挙げられますが、これらは変換効率が10パーセント前後から良くても20パーセント程度と効率はあまり良くありません。しかし非常に小型で軽量化ができることなどから宇宙用の電源として研究が進められています。
推進用原子炉
原子炉で発生させた熱を推進力として利用しようというものです。この場合大体は
- 原子力潜水艦
- 原子力空母
- 原子力巡洋艦
- 原子力砕氷船
- 原子力船
など、容積的にも余裕のある艦船で多く利用されています。他には
- 原子力航空機
- 原子力ロケット
なども考えられており、過去には試験等も行われましたが実用化には至っていません。
放射線源としての原子炉
放射線とは高いエネルギーの電磁波や荷電粒子のことを言いますが、これらを発生させて利用するには、
- 放射性物質を利用する
- 加速器を利用する
- 原子炉を利用する
という方法が挙げられます。
原子炉においては、
- ガンマ線
- 中性子線
が発生します。ガンマ線は特に「即発ガンマ線」と呼ばれ、核分裂で生じた核分裂生成物(核分裂片)が放射性崩壊によって放出するガンマ線と区別されています。
原子炉を用いると、加速器や放射性物質と比較して、放射線を多く照射できるというメリットがあります。
一方で加速器を用いた場合は、荷電粒子を電場で加速したぶんだけ、非常に高いエネルギーの放射線を発生させることができますし、放射性物質は特別な装置を必要とせずに単体で固有のエネルギーを持つ放射線を放出することができるため、そうしたそれぞれの特徴を生かして適宜利用されています。
原子炉で発生した放射線の利用方法は大きく分けると
- 発生した放射線を直接利用する
- 放射線によって特定の放射性物質を製造する
という目的があります。
発生した放射線の利用方法としては、医療用途や基礎研究、材料の研究などが挙げられます。材料の研究においては特に「照射試験」と呼ばれていたりします。これは、原子炉や人工衛星などに使われている材料が、強い放射線環境下でどのような状態になるかを調べたりします。
特に、その発生の仕方によって、ごく短時間のうちに大量の放射線を一瞬のうちに発生させることができる「パルス線源」と、安定して一定量の放射線を長時間照射させることができる「定常線源」に分けられます。
放射性物質の製造においては、医療用途や非破壊検査などにも用いられるもののほか、核兵器用のプルトニウムの製造に用いられる原子炉もあります。こうした原子炉は特に「生産炉」と呼ばれる場合もあります。
中性子を照射された物質は別の同位体へと変化し、それがアルファ崩壊やベータ崩壊と呼ばれる放射性崩壊を起こすと別の元素へと変化します。
| アルファ崩壊 | 中性子2個・陽子2個のヘリウム4原子核が放出されるため、原子番号が2つ小さくなる。 |
|---|---|
| ベータ崩壊 | 原子核の含まれる中性子の一つが電子を放出して陽子へと変わるため、原子番号が1つ大きくなる。 |
例えばウラン238が中性子を吸収した場合、ウラン239へと変化します。これがベータ崩壊を起こすと原子番号が1つ大きくなり、ネプツニウム239へと変化します。これがさらにβ崩壊を起こすとまた原子番号が1つ大きくなり、プルトニウム239に変化します。
ウラン238は「核分裂しにくい物質」ですが、プルトニウム239は「核分裂しやすい物質」です。上記のような過程を経ることで核分裂しにくい物質から核分裂しやすい物質を生み出すことができるというわけです。プルトニウム239の主な用途としては、原子炉の核燃料と核兵器が挙げられますが、原子炉の核燃料と核兵器では必要とされる組成に大きな差があります。核兵器に用いる場合はプルトニウムのすべての同位体に対して、プルトニウム239が占める割合が93パーセント以上である必要があります。また特にこの反応を、使用した核燃料以上に生じさせる事のできる原子炉を「増殖炉」と呼ばれます。